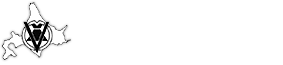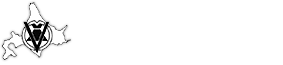第5章 飼育者の心得
動物との暮らしを好まないまたは出来ない住民も居ることを、動物の飼主は第一に認識しなければならない。非常災害時に避難生活を余儀なくされる場合に、これらの住民と他の動物飼育者との共同生活が円滑に行くように、動物の本能、習性、疾病などを理解するとともに、平時から動物に最小限のしつけと一般社会生活への協調性を学習させ、合わせて各種伝染病の予防処置と不必要な繁殖の防止策を講じておく必要がある。災害発生に際しては、必ず動物と共に避難をし、自宅への留置と繋留からの解放はやむを得ない場合以外行わない。このためには平時より、移動用ゲージ、リード、非常携行食並びに飲料水などを準備し、個体識別が可能な工夫(首輪・迷子札・マイクロチップなどで)も施しておくことが必要である。
このマニュアルは災害発生時において飼主と小動物との関係を維持するためにある。そのためには平常時から動物飼育に必要な事項と動物愛護の精神について理解し、終生飼育を基本とする飼主の責任と心構えについて記す。
〔飼主の心構え〕
小動物の飼主は次のことに心がける。
1)他の住民の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図る。
2)小動物の本能、習性、疾病などを理解し、動物の適正飼育、終生飼育に努める。
3)動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、各都道府県条例など動物に関する法律を守ること。
4)災害発生時に小動物と共に避難できるように、移動ケージ、リード、非常餌などを平常時から準備すると共に、個体識別ができるような工夫(首輪・迷子札・マイクロチップなど)を施しておく。
5)災害発生による小動物と離別、捜索の手がかりとして個体の写真を平時から用意しておくことも望ましい。
6)災害発生時には平常時に好んで食べる餌が十分に供給されない可能性があるので、好き嫌いの無い食生活をおくれるよう管理しておく。
7)疾病を有する小動物においてはその病歴、治療経過を飼主は十分に把握し、出来ればメモを作成しておくことが望ましい(様式5-1)。
〔飼主の守るべき事項〕
飼主は次に掲げる事項を守り、小動物を適正に飼わなければならない。
1)基本的な事項
a)小動物は常に清潔に保つと共に、疾病の予防、衛生管理に努める。
b)平常時から十分なしつけを行う。
c)飼育頭数は飼主が十分な管理を行える数にとどめること。
d)万が一の逃亡、不慮の離別から計画のない繁殖を防止するため避妊・去勢手術などの繁殖制限措置を行うこと。
2)他の住民に配慮する事項
a)動物との暮らしを好まない住民もいることを理解し、精神的な苦痛を与えないよう配慮する。
b)散歩時の糞尿などは適切に処理し衛生管理に努める。
c)社会通念上の限度を超える鳴き声を発する場合などは、獣医師などの専門家の指導を受け改善させる。
〔災害発生時〕
1)飼主は小動物と共に避難することが原則である。
2)やむを得ず小動物と共に避難できなかった場合は、個体についての情報、避難時の動物の状況を最寄りの救護動物保護センター、地方行政の動物担当部署、警察などに届ける。
3)小動物を救護動物保護センター、救護動物治療センター、または飼主と離れた別の場所で飼養する必要が生じた場合は、それぞれの管理者の指導に従う。
4)狂犬病予防注射、その他の伝染病予防注射の証明書など疾病予防管理に関わる書類を避難先に携行する。
5)災害発生により死亡した小動物は、公衆衛生上放置せず速やかに処理(火葬または埋葬)する事を原則とする。その際の処理計画、処理施設については行政の指導に従うこととする。
〔飼主の会〕
災害発生時に避難先となった避難所では、小動物の飼主などが集まり「飼主の会」を設ける。
1)「飼主の会」は、小動物の飼主全員と小動物を飼育していない居住者の代表も含めて構成し、避難所での適正飼育を計るよう運営する。
2)「飼主の会」の活動内容は次の通りとする。
a)会員は小動物の適切な管理に努める。
b)一緒に避難できなかった小動物の情報を収集する。
c)会員以外の居住者にも小動物と避難所暮らしをすることの理解を深める。
d)避難所内、周辺の衛生管理に努める。
e)避難所自治会との連携を保つ。
f)「飼主の会」の規定に反する飼主に適切な指導を行う。
g)自治体、動物救護対策本部、救護動物保護センター、救護動物治療センターとも連絡をとり、小動物の飼養管理の向上に努める。
h)避難所での小動物の飼育に不都合が生じた場合は、協議し善処する。
i)避難所で人獣共通伝染病が発生した場合、また疑わしい病状の動物が出た場合には獣医師、医師と連絡をとり対処する。
〔介護動物などへの配慮〕
盲導犬、聴導犬、介助犬などの介護動物とその飼主に対しては、近隣住民や他の小動物の飼主が協力し、災害発生時に優先して避難できるよう配慮する。
自治体にあっては、平時より介護動物を飼育する飼主の住所並びに氏名を把握しておくとともに、それらの動物の介護目的を確認しておくこと。
〔付記〕
1)ワクチンで予防できる犬の病気「犬ジステンパー」、「犬伝染性肝炎」、
「犬アデノウイルス2型感染症」、「犬パラインフルエンザ」、
「犬パルボウイルス感染症」、「犬コロナウイルス感染症」、
「犬レプトスピラ病」、「狂犬病」
2)ワクチンで予防できる猫の病気「猫ウイルス性鼻気管炎」、
「猫カリシウイルス感染症」、「猫汎白血球減少症」、「猫白血病」
3)小動物に関係する人獣共通伝染病
a)寄生虫性疾患「内臓幼虫移行症(犬回虫)」、「エキノコックス症」、
「トキソプラズマ症」など
b)細菌感染症「レプトスピラ症」、「カンピロバクター症」、「サルモネラ症」など
c)真菌感染症「皮膚真菌症」などd)その他「狂犬病」、
「猫ひっかき病」、「オウム病」など
4)マイクロチップについて
a)マイクロチップは、ボールペンの先くらいの大きさのICチップです。
全世界にたった1つの個体識別番号をICチップが記憶していて、
読み取りには器械(リーダー)を使用してその番号を読み取ります。
b)専用の注射器で背中の皮下に埋め込みます。
c)欧米、オーストラリアなどで普及していて、迷子になったときはもちろん血統の登録などにも有用です。