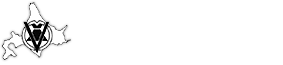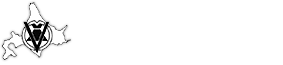第3章 ボランティア
救護業務の実際面に従事するボランティアを以下の様に区分する。
○救護動物保護センター(健常動物収容部門)
動物飼養ボランティア:主に動物の使用管理の仕事
一般ボランティア:事務、清掃、調理など直接動物に関わらない仕事
○救護動物治療センター(傷病動物治療部門)
ボランティア獣医師:獣医師として獣医療を行う
獣医療ボランティア:獣医療の補佐
動物飼養ボランティア:主に動物の使用管理の仕事
一般ボランティア:事務、清掃、調理など直接動物に関わらない仕事
動物飼養ボランティアは、動物看護士、訓練士、飼養管理士、動物看護士専門学校生および動物の使用管理に経験のある者に委嘱する。獣医療ボランティアは、獣医系大学学生、動物病院勤務経験のある動物看護士、訓練士、飼養管理士および動物看護士専門学校生などに委嘱する。
ボランティアの確保には平時において、各種ボランティアの登録制度を、
(社)日本獣医師会の地方会ブロックと同様に全国9ブロック
(北海道、東北、関東、東京、中部、近畿、中国、四国、九州)で完備し、
緊急時に速やかに全国的な招集が行われるようにしておく必要がある。
ボランティアの指導および統制を行うボランティア指導員の確保と講習会などを、上記9ブロック毎に開催する必要がある。講習会の指導内容は、小動物救援対策本部の役割、動物の飼育管理法、疾病および予防についての基礎知識並びにボランティア管理などについて行うものとする。
実際の活動に際しては、業務内容の確認と把握のため
随時ミーティングなどを開催し、収容動物と各ボランティアの健康管理に
対応していく必要がある。
災害時の動物救護では、実際に救護動物の飼育管理に携わる
ボランティアが相当数必要であり、
ボランティアの確保方法およびそれを管理指導する体制作りが最重要課題である。
ここでは、ボランティアの召集方法やその管理について、
平常時から行える対策と動物救護センター内での実際の作業上の注意点などにふれる。
〔ボランティアの区分〕
動物救護対策本部は専門知識、ボランティアの経験度、体力的問題および危険度などにより、所属部署や仕事内容を以下のように区分する。
○動物保護センター
動物飼養ボランティア・・・主に動物の飼養管理の仕事
一般ボランティア・・・・・事務、清掃、調理など直接動物に関わらない仕事
○動物治療センター
ボランティア獣医師・・・・獣医師として獣医療を行う
獣医療ボランティア・・・・獣医療の補佐
動物飼養ボランティア・・・主に動物の飼養管理の仕事
一般ボランティア・・・・・事務、清掃、調理など直接動物に関わらない仕事
動物飼養ボランティアは動物看護士、訓練士、
飼養管理士動物看護士専門学校生および動物の
飼養管理に経験のある者とする。
一般ボランティアはその経験などから所属部位を決定する。
救護動物治療センターに所属する獣医療ボランティア、獣医系大学学生、動物病院に勤務経験
のある動物看護士、訓練士、飼養管理士および動物看護士専門学校生などを委嘱する。
〔ボランティアの確保〕
1 ボランティア登録の実施
災害時にボランティアを安定的に確保することは困難な場合が多いために、平常時からボランティア希望者を募り、登録制とし、緊急災害時には登録者の中からボランティアを要請するシステムを構築する。ボランティア登録は緊急災害時動物救援本部が中心となって活動する。ボランティア登録はその専門知識により、獣医療ボランティア、動物飼養ボランティア、一般ボランティアなどに区分しておく。特に専門知識を要する獣医療ボランティア、動物飼養ボランティアについては平常時より動物看護士関係の専門学校や獣医系大学と取り決めを行い、緊急時に確実に人員派遣を行える体制を作る。この登録制は全国の9ブロックで個別に行い、その結果を集計し緊急災害時動物救援本部が把握するとともに、その情報を各ブロックにも保管し緊急時に全国的
な召集が行えるように準備する。
2平常時からのボランティア獣医師登録の実施
全国の9つのブロックに分かれる地区連合獣医師会単位で、平常時にボランティア獣医師の登録制を実施する
(様式3-1) (様式3-2) (様式3-3)
(様式3-4) (様式3-5) (様式3-6)
これにより、災害時に必要な医薬品や器材などの調達が把握出来るとともにボランティア獣医師や後方支援診療施設の状況をあらかじめ把握する。
この登録は、年1回更新し、常に最新の情報を把握する。また、緊急災害時動物救援本部が全国の登録情報を集計し把握する。また、各ブロックも集計した結果を掌握するとともにその情報を各ブロックにも保管し緊急時に全国的な召集が行えるように準備する。
3災害時のボランティア募集
災害時に動物救護対策本部は、登録された各職域ボランティアに召集をかけるとともに、新たなボランティアの募集を行う。ボランティア募集についてのマスコミリリースを行い、一般からも広く募集を募る。ボランティアの人員調整は緊急災害時動物救護本部と現地動物救護センターが行う。
被災者に対するボランティアと同様に災害対策本部内のボランティアセンター(社会福祉協議会など)からもボランティアを募集する体制を作る。
〔平常時からのボランティア指導員育成教育〕
1 平常時からのボランティア指導員の育成教育動物救護に当たっては相当数のボランティア人員が必要であるが、その指導および統制を直接行うボランティア指導要員が必要である。
この指導を行うボランティア指導員にはボランティアを統率する人間性や専門知識などが不可欠であり、
災害時に現場でこれらの適任者を見つけ災害ることが困難であるため、
平時より、緊急時動物救援本部が(全国9ブロックに分けて)指導員としての適格者の確保をするとともに、
指導者を養成する講習会を年1回、開催する。
指導員の候補者は、災害時に派遣可能な人材で適任者を、各団体から任命および依嘱する。公募する場合もある。
2ボランティア指導員育成講習会においての指導項目
1)動物救護対策本部の役割
2)動物の飼育管理法
3)疾病および予防についての基礎知識
4)ボランティア管理
〔ボランティア同意書への記載および現場での講習〕
センター内で円滑に仕事を行うためには、全員の意思統一が最重要課題である。
このため、ルールを乱したり自分勝手な行動をとらせないようにする必要がある。
このセンターの目的、活動内容、注意事項、禁止事項などを明文化しておき、
この施設の目的や活動内容を十分に理解し納得されたもののみ受け入れ、
ボランティア誓約書(様式3-7)に署名をさせる。
その場合、必ず規則を守って活動することを強調する。
ボランティア受付にてボランティア誓約書および
ボランティア受付表(様式3-8)に記載
が終了したボランティアはその経験により所属部所を振り分け、
その部署のボランティア指導
員が現場での仕事についての講習を行い、仕事を始めさせる。
〔ボランティアの生活環境〕
動物の救護活動は長期化し息の長い活動が必要となることから、ボランティアの安定確保の
ために、快適な環境を作る必要がある。
ボランティアが長期滞在出来るように、衣食住については出来るだけ快適な環境づくりをする。
1宿泊施設は男女別々に設け、浴室やトイレなど清潔な環境を提供しなければならない。
2食事に関しては、センター設置場所が郊外にあることが多く、
食事の調達も不便なこと、および動物の飼育管理が長時間の労働を
強いられることが予想されるため、センターで支給すること。
ボランティアの知識や経験度および人格などは多種多様であり、これらのことから人間関係上のトラブルが数多く発生することが予想され、これらの問題がセンターの運営に重大な支障をきたす可能性がある。このため、これらのトラブルを未然に防ぐために、監督および指導を十分に行い、場合によっては所属部署の配置換えおよび規則などを守れない場合にはボランティア契約の破棄などを考慮すべきである。
〔センター内での仕事のマニュアル作成〕
センター内の仕事内容について、マニュアルを作成し各自熟読し、仕事内容が把握出来るように心がける。
1 一日の仕事のタイムテーブルを作成し、それにそって活動する。
起床時間
朝食時間
朝のミーティング時間
午前の仕事
昼食時間
休憩時間
午後の仕事時間
午後のミーティング時間
就寝時間、など
2 ボランティア出勤参加簿への記入
後述のボランティア保険の関係や人数の把握の目的で、毎朝の仕事前に当日の仕事に参加するボランティアは全員、ボランティア受付簿に記入させる
(様式3-9)
3 健康管理簿の記載
救護動物保護センターにおいては、救護動物の毎日の排便排尿および食欲や異常な症状などを朝晩の給与時に健康管理簿に記入し、健康状態が誰でもすぐに判るように記録する。
4 ミーティングの実施
ボランティアの意志統一や連絡を確実に行うために、毎日朝晩全員の出席のもとにミーティングを行い、センター内での問題点や改善事項はこのミーティングによりボランティア全員に告知する。また、ボランティア指導員がその内容をミーティング記録簿に毎回記入し保管する。
(様式3-10) (様式3-11)
ボランティア獣医師の代表者は確実な仕事の引継を行い、その内容を業務日誌に記録する。
(様式2-1)
〔ボランティアの健康管理と休暇〕
ボランティアが長期化した場合に、疲労やストレスから体調を崩す場合があり得るので、
長期ボランティアにはある程度の自由時間や休日を当てるなど、
健康管理にセンター長は努める。
〔咬傷事故発生防止の指導〕
救護された動物は慣れない環境やストレスのために、凶暴化している場合が多いため、咬傷事故が多発する傾向がある。このため、一般ボランティアには注意しなければならない動物を明確にし、注意を払うように呼びかけることが必要であり、咬傷防止のために革手袋や口輪などを用意しておく必要がある。
これらの指導は常に犬舎の状況を把握しているボランティア指導員が行い、非常に攻撃的で危険な動物の場合には、センターでの保護活動を断ることが出来る。万が一、咬傷事故が発生した場合には、直ちに病院にて処置を受けることができるように、最寄りの病院を調べておく。
ボランティアの咬傷事故や不慮の事故に対応したボランティア保険(団体保険)に加入しておく。しかし、この保険で保証される金額は最小限であり、それを超えた保証はされないことにあらかじめ同意してもらうよう、ボランティア同意書内に記載しておく。